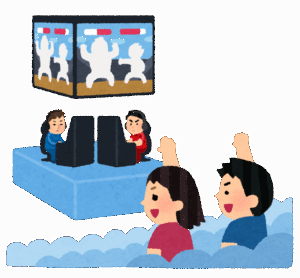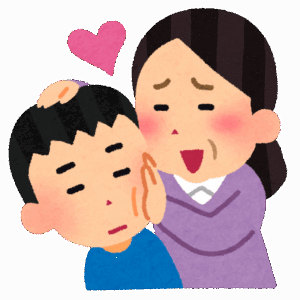\最新情報発信中/
不登校の正体

2023年度の児童生徒における不登校者数は34万6482人で、小学生は13万370人、中学生は21万6112人です。不登校の原因は様々ですが、その一つに「無気力・不安」といった具体的ではない対処に難しいものが多くを占めています。この原因に焦点を当てた書籍、「脇役になれない子どもたち ― 不登校の正体 ―:桑島隆二 著」が話題になっています。この書籍についてネタバレにならない程度に紹介します。
本書前書き(「はじめに」)の冒頭に、不登校児童を持つお母さんの相談があります。「『家族ルールを作って、デジタル機器を絶って、1日10回以上褒めましょう』とフリースクールに言われ実践したが全然うまくいきませんでした」というものです。このフリースクールの助言を筆者は荒唐無稽だと言っています。
不登校児童生徒に対する接し方でよく聞かれる、
1.無理をさせない
2.優しく接する
3.丁寧に気持ちを聞いてあげる
という決して間違ってはいない対応が解決に向かわない現実に学校も家庭も行き詰っている現状を指摘しています。
この著書は、冒頭の「荒唐無稽」な理由と3つの対応が上手くいかない理由を今までにない視点から論じています。核心部分の紹介はネタバレにつながるので、本書全7章の章タイトルを紹介します。ここから内容を推察してください。
第1章 「みんな主役」によって特別感を抱いた子どもたち
第2章 自己評価と自己肯定感の勘違い
第3章 自己評価が高まると他人を見下す
第4章 自分は脇役だと気づいたとき、不登校が始まる
第5章 どうして不登校の理由が言えないのか
第6章 子どもに特別感を抱かせない関わり方
第7章 いま不登校の子どもたちをどうするのか
最後に参考となるレビューも1つ紹介します。
レビュータイトル:「とにかく褒めて伸ばそう」への警鐘
本書は、不登校の増加という現象と対処にとらわれて、その本質的な原因を見失っているという鋭い指摘を投げかけています。傾聴や共感・自己肯定感といった心理学の概念が世間に広まるのは悪くないことですが、「とにかく褒めてあげること」とか「子どもに嫌な思いを一切させないこと」とか「子どもの言うことは全部聞いてあげること」とかが自己肯定感を高めることで共感するということだ!というような風潮が広まっている現状を鑑みると、一般の方だけでなく残念ながら支援職に携わる人でさえ、概念の理解は表層的な部分でとどまっているような気がします。今現在子どもたちに関わっている職業の方にはもちろんのこと、そうでない方にもためになることが書かれている一冊です。
不登校にお悩みの方、特にその原因がはっきりしていない方はこの本を手にとってはいかがでしょうか?解決の糸口になれば幸いです。