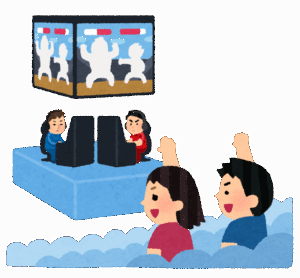\最新情報発信中/
必要なのは「仲良く」ではなく「共存」
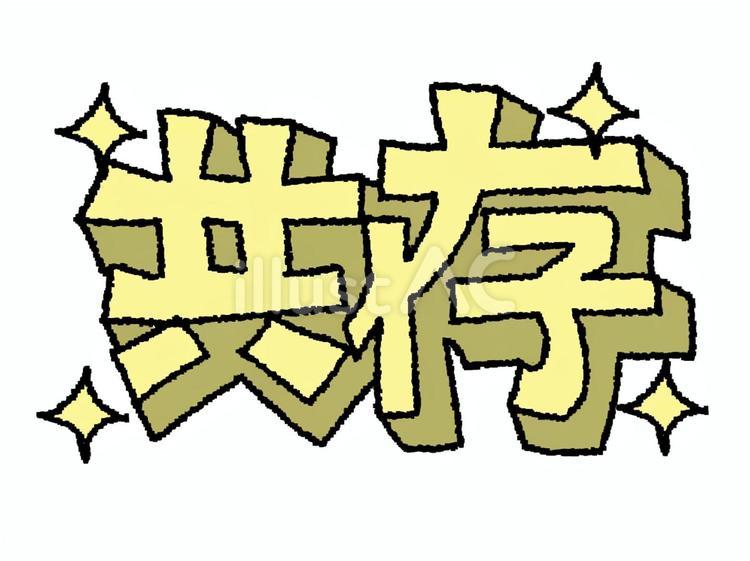
教育についての様々な記事やコラムがある「東洋経済education×ICT」をよく読みます。
今回はその中で気になった記事を紹介します。タイトルは「戦時教育の名残『みんな仲良く』が子を追い込む、仲が悪くてもいい『教室で共存の練習』を 好き嫌いを超えて協働できる力が求められる」です。その中でもこのコラムのタイトルにした「必要なのは『仲良く』ではなく『共存』」という見出しのところです。
「好き嫌いを超えて協働できる力」とも言い換えています。それは、好きではない相手とでも同じ目的のためには協力できる。さらに目標達成の際には一緒に喜ぶことができる力です。かつて、「みんなと仲良くしなさい」とよく言われ現代の教育現場においてもその雰囲気は残っています。
「誰とでも仲良くできないのはダメ」と思うと学校が苦しい場所になる児童や生徒が相当数いるはずです。学校というコミュニティーは、単にお勉強をする場所だけではありません。大人になり社会で上手くやっていく訓練をする場所としてもあるべきです。社会に出ると「誰とでも仲良く」なんて建前にすぎません。むしろ、嫌いな人とも上手くやっていくのが利口な生き方でしょう。
学校に仲良くできない人がいるというのは問題ない。ことさらにその相手を意識してその相手から逃げたり、対立したりすることなく共存できれば良いのだと子どもたちに教えることが必要です。
そのほか、「『仲良くできない』も大切な学び」という興味深い見出しもあります。全文が気になる方は、是非上記リンクよりお読みください。